認知症の母が相続人である場合、名義変更はできるのか?
相続登記の義務化に伴い、数年前に他界されたご家族の相続登記を
これから頼みたいというご依頼が、たくさん寄せられております。
今回は、以前実際にご相談いただいた「相続人である家族に認知症の方がいるケース」をご紹介します。
ご相談内容:数年前に他界した父名義の不動産を売却したいが、母が認知症…
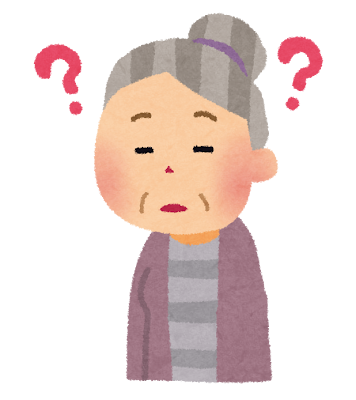
ご相談者様のお父様の相続につき、相続人は以下の3名です。
- お母様(法定相続分 1/2。お父様と同居されていたが、現在はショートステイを長期利用しながら高齢者施設に滞在。)
- ご相談者様(法定相続分 1/4。長男。市内に在住。)
- 妹さま(法定相続分 1/4。ご結婚され、県外在住。)
ご相談者様は、お父様が他界され、高齢のお母様も施設に移られた今、
空き家状態のご実家をいずれ売却したいとお考えでした。
県外にお住いの妹様も同意されています。

故人名義の不動産はそのまま売却することが出来ないため、この度の相続で
「売却の前提として不動産のご名義をご自身に変えたい」というご希望でした。
しかし、問題がございました。
お母様がすでに認知症を患っており、法律行為ができる状態ではないということです。
問題点:遺産分割協議ができない
遺言書がなかったため、不動産をすべてご長男である依頼者様のご名義にするには、
相続人全員による遺産分割協議が必要でした。
ところが、お母様が認知症であるため、協議に参加できません。
このような場合、以下のような選択肢が考えられます。
選択肢1:法定相続分で相続登記を行う
協議をせずとも、民法で定められた相続分(母1/2、兄1/4、妹1/4)で登記をすることは可能です。
メリット:
- 協議が不要なので、すぐに登記できる
- お母様が認知症であっても名義を変えられる。
デメリット:
- 名義人の一人であるお母様が認知症である限り、お母様の持分についてはその後に売却手続きができない。
- 将来、お母様が亡くなった際に再度相続登記が必要になり、手間と登録免許税が余計にかかる。
この方法の場合、不動産すべてを即時にまとめて売却することはできず、理想の状態とは言えません。
選択肢2:お母様に成年後見人を立てて協議を行う
お母様に代わって法的な意思表示を行える「成年後見人」を家庭裁判所に
申し立てて選任することで、遺産分割協議が可能になります。
メリット:
- 遺産分割協議ができる
- 不動産を希望通りご自身の単独名義にして売却できる
デメリット:
- 申立てに時間と費用がかかる
- 後見人はお母様の財産を厳格に管理する必要があり、不動産の売却や管理にも家庭裁判所の許可が必要になる場合がある
- 登記後も、後見制度が継続し、面倒な手続きが続く
売却を急ぐのであれば成年後見制度は大変有効ですが、その後の運用の負担が大きくなる
という点は理解しておく必要があります。
選択肢3:相続登記をせず、お母様の相続を待つ
「いまは無理に登記せず、次の相続時にまとめて手続きをする」という選択もあります。
メリット:
- 余計な費用と手間がかからない。
- 近日内の売却は出来ないが、お母様のご相続発生時に兄妹で分割協議をし、空き家として売却をすれば譲渡所得税などの減税措置が受けられる場合がある。(減税の細かい条件に当てはまるかを事前に検討する必要がある。)
デメリット:
- 相続登記義務化の過料が2027年4月以降発生する可能性がある。
2024年から相続登記が義務化され、2024年4月1日以前に亡くなった方の相続登記は
2027年3月31日まで(それより後のケースは相続発生時から3年以内)に申請しなければ
相続人一人につき最大10万円の過料が科される可能性があります。
今回のケースでは数年前に他界されたお父様の相続登記につき、三名の相続人で
最大30万円の過料のタイムリミットが迫っています。
結論:今回は相続登記をせず、相続人申告登記で過料を回避する。
ご相談者様が選ばれた方法は、「相続人申告登記」を行うというものでした。
これは「まだ名義変更はしないけれど、相続が発生したことを法務局に報告する」と
いう制度で、登記義務を果たしたとみなされ、過料の制裁を回避できます。
ポイント:
- 登録免許税は不要
- 戸籍収集などの費用はかかるが、将来の相続登記時に使い回すことも可能
- 認知症のお母様は申告人になれないが、ご自身と妹様だけでも申告すれば、過料のリスクは大きく軽減される
今回のご依頼者様は、売却を急がれてはいなかったということと、
お母様のご相続が発生するまで待ったとしても「空き家売却の特例措置」
(No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁)が
適用される条件に当てはまる可能性が高いということで、このご判断に至りました。
相続人申告登記は確定的に権利を移転するものではなく、一時的な措置ではありますが、
このケースのように分割協議ができないという事情がある場合には有効な手段です。
まとめ:相続対策は「家族みんなが元気なうちに」
今回のケースからもわかるように、認知症になると相続手続きは非常に複雑になります。
もし、誰にどの財産を渡すかが決まっているのであれば、自分だけでなく
家族も元気なうちに今後を話し合ったり、遺言書を作成しておくことが何よりも重要です。


司法書士は、相続や遺言に関するご相談も承っています。
「何から始めたらいいかわからない」という段階でも、お気軽にご相談ください。


お気軽にお問い合わせください
スタッフ一同
お待ちしております